病院建築の新処方せん
〜医療施設と福祉施設を複合〜
ソフトもハードも地域密着
福祉との連携で地域に密着した医療が求められているのは、大都会に限ったことではない。医療施設と福祉施設の複合化は、高齢社会において一般解だ。
秋田県南秋田郡にある医療法人の正和会は、95年から複数の診療所を1箇所に集めた「昭和ヘルスケアビレッジ」を運営している。敷地内には、形も大きさも違う五つの建物がコテージのように点在する。診療所のほかに、介護老人保険施設「ほのぼの苑」、訪問看護ステーション、在宅総合ケアセンターも併設されている。
このような複合施設は、以前から地元で開業していた正和会の小玉敏央理事長らが、ニーズを感じて計画したものだ。医療施設と福祉施設を両方運営することは、福祉施設の入居者にとっても、施設運営者にとってもメリットが大きい。施設に入居する高齢者にとっては、何かあったときに医師が駆けつけてくれるという安心感がある。各施設の運営は独立採算で会計も別々だが、広報宣伝費や施設の清掃費などをまとめて委託することで、効率のよい運営ができる。
診療所をひとつの建物にまとめずに独立させたのは、その方が地域に溶け込みやすいと考えたからだ。各施設は一見するとばらばらに建っているように見えるが、歯科を除いたすべての建物が渡り廊下でつながれていて、職員や患者は屋外に出ることなく行き来できる。
正和会の平野昇司企画管理部長は「大きな病院には、いくら新しくてきれいでも、独特の硬いイメージがある。地価が高い都市部では無理だろうが、患者にとっては平屋で小さい施設の方が親しみやすい。上下の移動もせずに済む」と話す。運営の面からも、建物が別々の方が医者同士の関係に適度なクッションができ、意見がまとまりやすいと言う。
正和会では現在、隣接する敷地にグルーブホームの建設も計画している。新しい施設を建設する時には、診療所の医師やスタッフが集まって建設委員会をつくり、意見を出し合う。医療や福祉の現場の声を反映しながら設計を進められるのも、複合運営の利点だ。
地域に溶け込むためにイベントも
昭和ヘルスケアビレッジの中で一番目立つのが、99年の夏に竣工した内科の医院だ。幅20mほどの外壁一面に、虹や山の絵が描かれている。地域の住民になじんでもらおうと、子どもたちを集めて描いてもらった。
壁画の企画を提案したのは、医療デザインのコンサルティングを手掛けた石田章一・ビジョン代表。小玉理事長が、知り合いの石田氏に相談したことから実現した。「設計のワークショップや外壁のペイントなどのイベントを開くことは、新規患者を増やすよい手段でもある。地域の子どもが参加すれば、親も見に来る。初めての病院にはなかなか行きにくいものだが、医師の顔や施設の雰囲気を知っていれば、いざ病気になったときに足を向けやすくなる」(石田氏)。正和会では施設入居者と地域住民との交流を深めるために、夏祭りや花火大会などのイベントも積極的に開催している。
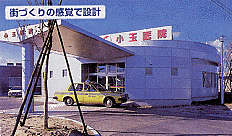
▲内科
|

▲内科のナースステーション
|
「建物内部は共通した素材も使用しているが、外形はあえて統一せずに、自然な街をつくるような感覚で設計した。それぞれの診療所の個性を出すように心掛けた」(小野泰太郎代表)

▲眼科
|

▲歯科
|
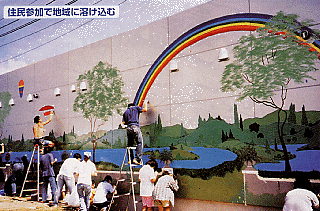
▲内科の外壁に色を塗る近隣住民
|
|