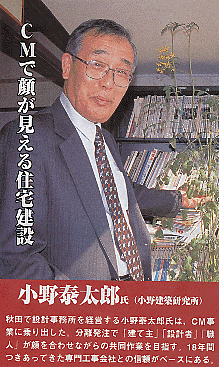
秋田市で社員12人の小野建築研究所を主宰する小野泰太郎氏は、1998年に社内にCM(コンストラクション・マネジメント)事業部を立ち上げた。各専門工事会社が建て主と契約する方式を導入し、発注業務を代行する。これまで住宅25件で実践した。住宅は100%CMで臨んでいる。
建て主にほめられるのが誇りに
CMを立ち上げた一番大きな理由について「職人と建て主と設計者が一緒になって取り組むのが、本来の家づくり。建設会社に任せず、互いに顔を見せながら、手作業で取り組みたい」と小野氏は語る。
その思いとはうらはらに、現場では職人たちが「どうせ俺たちは下請け、孫請けだ」と投げやりな仕事をしている。「分離発注を導入すれば、施主からもろに怒られる。直接ほめられることもある。それが、やりがいだ。じかのやり取りが誇りや自信になる」と小野氏は思う。
バブル以降、職人を抱える専門工事会社の苦境は続き、友人の会社は倒産した。「職人で成り立っている日本の建設産業が、このままではだめになる」。この状況を救うにはシステムを変えるしかない。CMを導入したのはそのためでもある。
小野氏をCM方式に向かわせる素地は、18年間におよぶ専門工事会社の友人たちとのつきあいでできていた。ただの酒飲み友達が、いつしか勉強会を開く仲間になった。4、5人だったメンバーは、最終的に約50人へと膨らんだ。
勉強会から、現在の一括発注方式が戦後生まれのシステムだと知った。小野氏にとってCMとは何も新しい方式ではなく、建築本来の姿に立ち返ろうとするものなのだ。
99年に成果を「実施要領」にまとめた。「仕事を取るための組織になると説得力がなくなる」(小野氏)と、それまでの勉強会を解散した。
ブラックボックスだった価格を開示
CM業務の手順はこうだ。設計が完了すると、ひとつの工種について2、3社の秋田市内の専門工事会社を指名して説明会を行う。工種は10以上。各社から見積もりを取り、建て主の前で開封する。提示額の安い会社と価格交渉を行い、契約する。
「住宅で下請けの見積もりが建て主の手元に行くことはこれまでなかった。“ブラックボックス”だった価格をすべてオープンにし、1円たりとも不明なお金がないようにした」と小野氏は話す。一括発注に比べると、施主は2、3割、工事費を下げることができるという。
説明会の時間は各社ずらして、互いに顔を合わせないようにする。談合を回避するためだ。ダンピング競争にならないように、いずれは見積書に「利益」という項目を設けたいと思っている。
お金もうけにCMは向かない
これまで住宅の設計業務で工事費の5〜6%だった収入は、CM導入で12%になった。設計4%、工事管理、業者選定、発注業務が8%の内訳で、「もうけはない。大きい物件もやらなければ苦しい」金額だ。
専門工事会社の側はどうか。実は、請負金額は、建設会社の下請けでも、分離発注で建て主と直接契約しても、それほど変わらないという。それでも、ある設備会社の社長は「建設会社にもうけられている、という感じがしない」と好意的だ。値引き金額がそのまま施主に伝わるため、サービスが還元されたと実感する。
小野氏は、苦しい状況にある林業を再生させるため、専門工事会社のひとつに林業を入れることも考えている。「CMが軌道に乗ったら業務を切り離し、あとは独立して一人で住宅を設計するのもいい」と最後に夢を語った。
  |
|