「技芸の人」林業家・加藤周一さんの特集記事のなかで、当CM方式が紹介されました。
■施主と各業者が個別契約
ここ10年ほど加藤周一さんは、加藤家の木を使った「産直販売システム」の家づくりを行ってきた。やりがいはあるが、慣れない新しい分野の仕事でもあり、家づくりの段取りをすべて仕切っていた周一さんは、施工業者に翻弄されることもあったという。
そんな周一さんは、今年から小野泰太郎さんとパートナーを組んでいる。小野さんは鶴岡市三瀬地区の出身で周一さんとは親戚関係にもあるが、秋田市内で株式会社小野建築研究所を経営し、CM方式(コンストラクション・マネジメント)で建築を実践している。
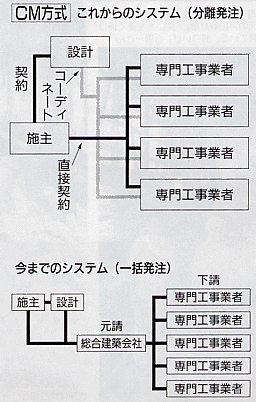 |
CMは「分離発注方式」と呼ばれ、施主が施工業者を施工内容別に選択し、施主と各施工業者が個別に契約を行うという方式。従来のように、施主から元請け業者が工事を受注し、下請け、孫請けの施工業者へと流す方式とは大きく異なる。
例えば、CMでは工務店も左官屋もそれぞれが直接施主と契約し、設計業者が施主の立場に立って、施工業者をコーディネートする。施工業者のすべてが元請けとなるので、仕事に対する職人としてのやりがいが増す可能性もある。
「施主にとっても職人と接する機会が増え、本当に家を建てているという感覚になれる」と小野さん。
また、小野さんは「ユーザーに対しては、1円たりとも不明なお金があってはいけない」と話す。契約前の合見積もり等による業者間の競争やコストの透明化で、CM方式によって全体の建築コストを2〜3割程度削減できるという。 |
取材時に鶴岡市で建設中のIさんの家は、周一さんにとってCM方式での1棟目になる。周一さんにとって施主は周一さんの木で建てたいというお客さんだが、CM方式では周一さんも施主と契約する一業者である。「これまでは私が家づくりの全部を仕切っていたけど、CMで材木に集中できる。良いものを安く、施主が喜ぶような材料を提供したい」と周一さん。
周一さんは施主のIさんに製品1石(0.28立方メートル)当たり2万1000円で180石納品した。金額は製材所に支払う賃挽き料(1石当たり5500円)込みである。
■立木80年生は商品に見れない
小野さん自身はCM方式ですでに30棟ほど手がけたが、CM方式に周一さんのような林業家が参加することを想定していなかったという。今は林業家と一緒に家づくりすることは非常に良いことだと考えている。
「周一さんと一緒にお客さんを山に案内するんですが、お客さんは『ほぅー』と感心するわけです。柱と違って、山の80年、100年の樹は商品としては見れないんですね。山の精神性を感じるんです。これは私が長年設計事務所をやってきて初めての経験でした。お客さんは住宅展示場をいっぱい見て、いろいろな情報を持っている。ただ、どれが正しいのかという確信は持っていない。混乱しているんですね。山に来て頭の中のもやもやしていたものが、すぱっとなくなって、この山の木を使えば絶対大丈夫だと。山の持っている精神性をユーザーが感じることが、家づくりの一番基本だと感じたんですね」
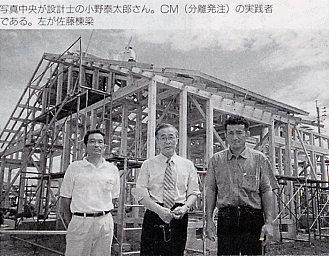
|